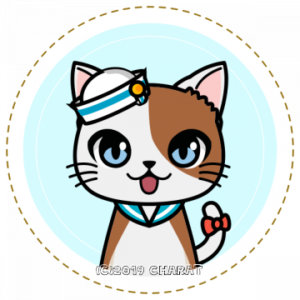こんにちは、Happycat (@Happycat3meow) です。
近年売れ行きが急増の気配がある、ポータブル電源。
理由は主につぎの二つでしょう。
①レジャーを思い切り楽しみたい。
②有事や、災害対策として。
とくに最近は後者が多そうです。
でも、高額なお買い物なので、失敗しない選び方をしたいところです。
いざ取りかかってみると、「災害用のポータブル電源選び」って意外と奥深いんですよね。
今回は、わたしと同じようにまったくポータブル電源選びが初めての女性でもわかるようにご案内します。

読み終わる頃にはポータブル電源選びが楽しくなるかも!?
もくじ
初めて防災用ポータブル電源を買うとき、ネックになるのは?
そもそも「電気がない環境でも、電気を使いたい」という、用途自体はシンプルなはずのポータブル電源。
しかし!
現代はあらゆる電化製品があふれて、電源の接続方法やパワーなどもさまざまです。
それに合わせ、ポータブル電源側も、
電気を溜める(入力する)方法、電化製品をつないで使う(出力する)方法にも、それぞれいくつもの種類があるんですよね。
これを、できる限り自分に合った条件が揃い、不要な機能は抑えた機種を選び出す必要があります。
さきほど言ったように、そこそこ高額なお買い物なわけですから。

必要性に合ったポータブル電源を選ぶには、ある程度は勉強しないと選ぶ基準もわかりません。
そこが面倒くさいところですが、実際いくら欲しくても勉強時間自体が取れず、なかなかわたしも購入に辿り着けませんでした。
最初につかもう!防災向けポータブル電源の基本イメージ
近年ますます必要とされてきているポータブル電源は、
より多様な要望に合わせ、大きさや性能もどんどんバラエティ豊かになってはいるようです。
ですが基本的な商品の特徴はどうしても大きくて重たいんですよね。
「くりかえし充電可能な乾電池=蓄電池」がたくさん内蔵されてるとイメージすれば、重いのも仕方ないのでしょう。
最小のモデルでもそれなりの重さです。

しかも今回選ぶ基準は、「防災重視」!
キャンプなど軽い目的には小型でもそう不安はないのですが
性能やパワーの基準がレジャー用途よりも大きくなる点は、押さえましょう。
性能やパワーの単位が多すぎて混乱!まずは何から押さえればいい?
大きめになることはわかったけど、単位もボルト(V)だのワット(W)だのアンペア(A)だの...。
その上まだWhとかあって、単位の数だけでも大変!これじゃあ選ぶ基準がわからなくてなかなか買えない!
というそこのあなた。そのとおりだと思います。
わたしがつまずいていたのもまさにそこでした(-。-;
一般にこの方面は苦手な人のほうが多いでしょう。
理系の人はこんなとき有利ですけどね。
そこで...。
まずはこの式だけ押さえると早いと言うことを発見!
かけ算九九のように頭に入れてしまえば、その後がう〜んと楽になりますよ♪(九九より少ないし)
アンペア(A)×ボルト(V)=ワット(W)
これを言葉で言い換えると、
電流(電気が流れる量)×電圧(電気の強さ)=消費電力
まずはシンプルに、このW数(消費電力)を基準にしてポータブル電源をみてみましょう。
なぜかといえば、W数が20であればその内訳は、たとえばA2×V10=20WとA5×V4=20Wと、AやVの組み合わせの変動はいくつか考えられても、総力となる20Wは同じですよね。そこがポイントだからです。
そしてWhは、ワットアワーといい、「1時間に消費する電力」のことです。
実はストレス対策も防災時は必要!
さて話しは一旦飛びますが、災害時に最重要なのはもちろん食糧や水ですね。
寒暖対策も大事です。
ただ、意外と見落としがちなのが「ストレスを極力減らすこと」。
災害時・有事の時は、それまでの暮らしの快適さからガタっと落ちますから、
そのストレスは未知数と言えそう...。
災害時にこそ大事な健康や免疫を保つためにも、疲れやストレスはできるだけ減らすことが重要です。
そしてそれは難しいことではありません。
ちょっと想像力を働かせてみると、かなりの割合を事前に対処できるでしょう。
この後は「ストレス対策」の視点も取り入れた簡単な前準備をご紹介します。
ポータブル電源選びにも取り入れてみると良いかもしれません。
もし、停電や災害が起こったら?絶対に使う物をリスト化する
もし環境が突然不便になっても、あなたが変わらず使えるだけでも落ち着くものは何でしょうか?
今回は電源がテーマですから、電化製品に絞って考えましょう。
例えば使い慣れた炊飯器や、乾きが早くてお気に入りのドライヤーがあって、
災害時にも、変わらずそれらが使えれば、大変な中できっとかなり安心ですよね。
まずはそういう電化製品を全部書き出して、リスト化してみます。

さて、簡単なリストができましたね。
次に、それぞれの電化製品の「W(ワット)数」を全部書き出します。
W数は、製品のどこかまたは説明書に書いてあるので探しましょう。
それらのW数を合計したものが、災害時の生活の落差を最小限にする目安となる消費電力です。
まずはこのリストを基本に、必要な電源量を考えていきましょう。
意外と消費電力が高いコレ!買い替えるか、対処法は色々
さて、少し前に例題としてドライヤーを出しましたね。
実は、一般的なドライヤーは1000W以上と、かなり消費電力が高い部類なのです。

例えば電子レンジも、消費電力自体は高いです。
でも、温めるだけなら10分と使いませんよね?
しかしドライヤーは、髪の量や長さにもよるけれど結構乾くまでの時間は使います。
ですので愛用品とはいえ、ポータブル電源の貴重な電気を大量に使う可能性が...。
ここでさっき覚えたWh(ワットアワー)の計算練習をひとつやってみましょう♪
1000Wのドライヤーを15分使うと、1/4時間。
1000Wをそれで割ると、15分で250W消費するというわけです。
ただ、これもあくまで簡単に考えた理論上のこと。
実際にはポータブル電源から電化製品に電気が流れる時点で、いくらか電力を失うロスもあったりします。
おまけにたまたまお天気にめぐまれないと、太陽光パネル→ポータブル電源へと電気を溜めるにも相当な時間が必要に...。
この場合は、
A.ドライヤーを短時間だけ使う
B.髪をカットする
C.多少高くても消費電力が少ない新型ドライヤーに買い替える
という具合に、いくつもの選択肢が生まれます。
どの方法がベストかは人によりますが、こういうことも考えておくとなお良しですね。
(わたしも使ってるドライヤーをみると....ズバリ1200Wでした!電気代も上がっていくご時世なので思案中です(-。-;)
改良案を考えた場合の消費電力も出してみよう!
このように考えていくと改良策も奥が深くなってきます。
さきほどのリストが、リスト①だとすると、消費電力をけずった改良版リストを作っていくことになります。
簡単なものでOKですよ。
仮でもざっと作ってみることで、目安がわかるのです。
例えば、もう一つの例題ではドライヤーより重要度の高い炊飯器。
炊飯器のW数は実はドライヤーよりはずっと少ないのですが、電気が通らなければかなり場所はとってしまいます。
ご飯が炊けることは大事ですが、それまでの炊飯器以外の方法でも炊ける道具でやってもいいなと思えたら、また違ってきますね。
ここであらためて全てのリスト①の電化製品を次の視点で見てみましょう。
A.手放さずそのまま使い続けたい電化製品
B.電気以外の方法に変えても構わない電化製品
C.初期投資は必要だが長い目で見て節約になるエコな新型に買い替えられる電化製品
この方法で見直した上で、あらためて総合消費電力を計算します。これがリスト②。
こちらもまとめてみましょう。
リスト①=災害時でも使い続けたい家電全てのW数の合計
リスト②=①の中で電気以外やエコタイプに取り替えてもOKなものに工夫した上でのW数の合計
このリスト①〜②のあたりのW数がその人の日常での基本消費電力です。
さらに、家族と共同で使う電化製品と各個人が使う電化製品の消費電力(W数)を合計してみます。
そうすると、ポータブル電源の最低限必要な大きさ(W数)の見当もついてくるでしょう。

ちなみにエコタイプに買い換える場合、出力タイプが大事です。
出力にはACとDCと二種類のタイプがあるのですが、DCのほうが商品は若干高めですが、災害時には遥かにエコです。
冷暖房や大型家電はたしかに考えもの?工夫の道は意外とある!
さて、おおよその電化製品の日常の使用量はこれで掴ると思いますが、問題は季節による消費電力の変化ですね。
特に真夏と真冬は、冷暖房が最も電力を消費しがちです(-。-;
ただ、これも工夫のしどころ。冷暖房と言っても消費電力はいがいとまちまちです。
また、できるだけ電気以外の方法を考えてみましょう。
冬の場合ならカセットガスストーブ、カイロ、可能なら薪ストーブなんていうのもあります。
ちなみにそれぞれこんな感じですね。
寝袋や極暖のダウン入りの服を買っておくなどもいいし、工夫すればかなり頭の体操になるかも(^◇^;)
ここは年間の電気の必要性を見通して、計画的に買い物予定を立てていきましょう。
簡単に考えておくだけでも違いますよ!
一見単純な「ポータブル電源を買う」と言う目的も、掘り下げればなかなか深いものです。
合わなかったらどんどん買い替ればすんじゃうお値段ではないし、タイプも色々ですからね。
また冷蔵庫も、考慮したくなるでしょう。
ただ、簡単に調べてみところ、意外と電力は少なくてびっくりしました(150〜500W)。
ミニタイプの冷蔵庫というのももあるにはありますね。
ここでも工夫は可能で、例えば日持ちしない野菜も乾燥野菜などと併用すれば保存期間の心配も大きく減らせます。

課題がすべて消えるわけではないですが、全く見当がつかなかった最初よりはぐっとめどが立つようになったはずです。
なにしろ災害時対策なので、ポイントを抑えるのが大事です。
完璧主義はこの際、少しずつやめていけばストレスも減らせますね。
実際にはどれくらいの大きさのポータブル電源がいいの?
ざっと計算でおおよその「自分はこれくらいの電力は使うんだな」...という基準がわかったと思います。
結果も保存しておけばいつでも見直せますね。
わたしも全ての電化製品はまだ出していませんが、調べてみました。
たとえば電子レンジは50Hz(ヘルツ)使用で930W、60Hz(ヘルツ)使用で1350Wでした。
炊飯器は495W。
ただ、もっと急いで買いたい時。
とにかく性能がいいのを選んで工夫して使えばいいのでは?という意見もあるかと思います。
そこでも大事なのは、どんな大きさが自分にあっているのか?
手っ取り早く選ぶ基準はもちろんあります!
さきほどお話ししたようにドライヤーだけで、1000W以上の消費電力でした。
夜は、灯りをつけながら寒暖の電化製品を使ったり、並行利用したいことのほうが多いでしょう。
そのことからも、災害対策のポータブル電源は、理想で最低限1000W以上は欲しいところです。
これなら、工夫しながら冷蔵庫も数時間はつなげることが可能となります。
防災用ポータブル充電で他に重視すること
供給電力の大きさ以外は下のことを重視しましょう。
防災なのだからソーラーパネル充電が大事!
これはいちばん重要事項のひとつかもしれません。電源を取り込めなくなってただの箱になっては大変!!
通常から使う練習をするときには普通の電源でチャージしてみて、そのあとソーラーパネルを使う練習をすると良いでしょう。
ただ、太陽発電というのは通常の電源とは違い、時間は何倍もかかります。またパネルには少しの影でもかなり影響があるとされるので、うまく使えるようになりたいものですね。太陽光にいつも垂直にパネル面が当たるのが理想のようです。
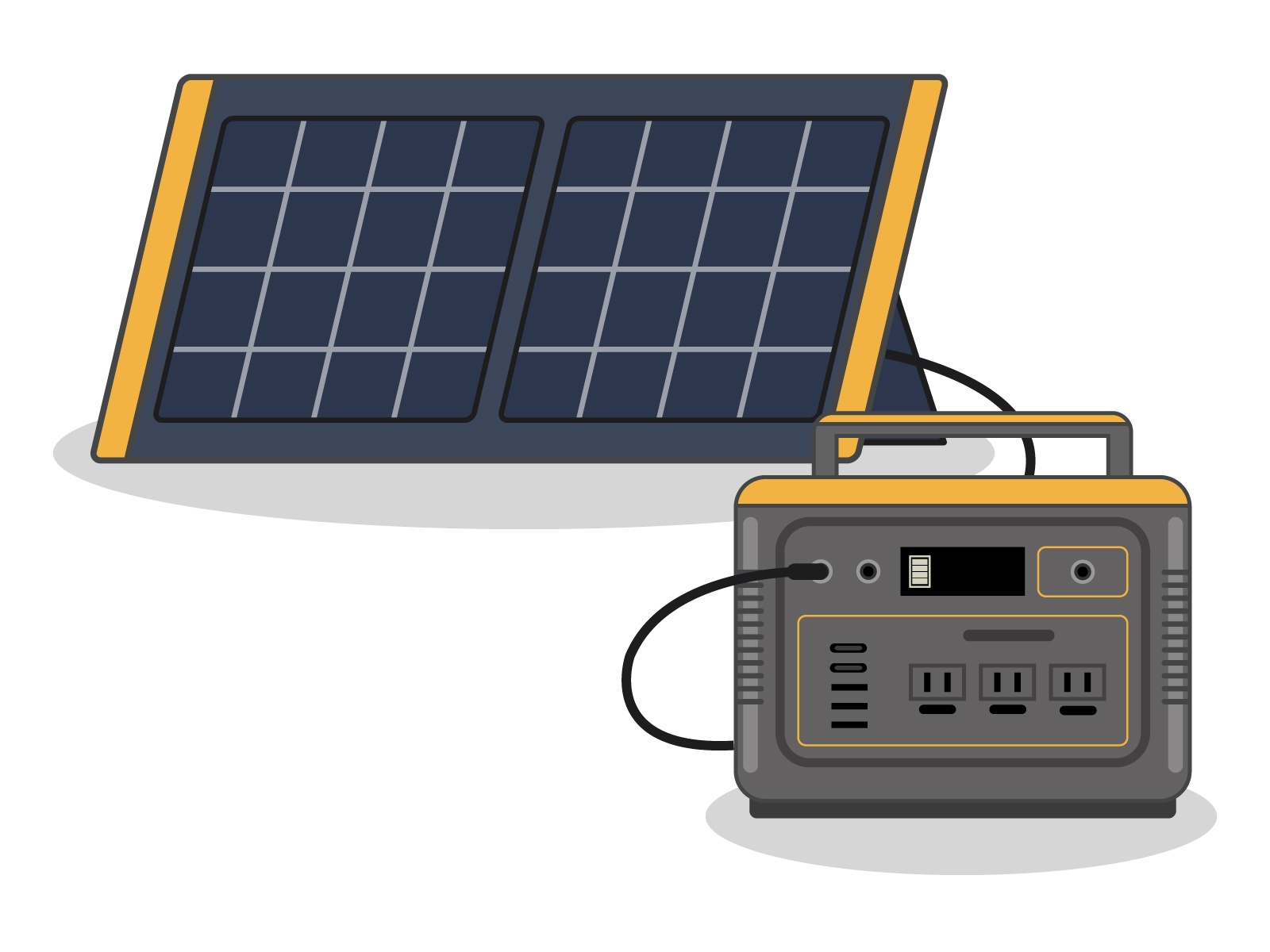
バッテリーの種類と選び方
次に大事なのは、バッテリー(蓄電池)の種類です。
ポータブル電源に使われるバッテリーは、現在二種類。
・リチウムイオンバッテリー
・リン酸リチウムイオンバッテリー(LiFePO4、LFPとも)
基本的にはどちらも安全だとみなされています。
ただ、まれな確率で発火する確率が高いのはリチウムイオンバッテリーで、LiFePO4はより安全度が高いとのことです。
防災用におすすめのポータブル電源はこれ!
ポータブル電源はそれこそたくさんの種類があります。
時間短縮のためにも、まずは上の二つからわたしがすぐに辿り着いたベストなものをご紹介するのが早いでしょう。
ベストメーカーは、エコフロー(EcoFlow)社がいち押しです。
ラインナップは大きく二つに分けられ、レジャー用(1000W以下)のリバーシリーズ、そして今回の対象である災害対策用のデルタシリーズです。
デルタシリーズは持っているだけでひとまず精神的に落ち着くレベルですね。
もちろん大きくなるほど大船感がありますので、極端にいうとあとは費用配分やお財布との相談だけと言っても良いでしょう。
小さい順に並べていきましょう。下へ行くに従って大容量になります。
まずはデルタ mini。
デルタシリーズで最もお財布に優しいタイプかつ、唯一災害用で1000W以下のタイプです。性能は全タイプ通してばっちりなので安心。
また、充電もエコフローは驚異的な速さが魅力です。
このDELTAシリーズ以後 から1000W超えとなります。記事を書いた当初新しく加わった新モデルで最初は「DELTA 1000」でした。
バージョンアップを重ね「DELTA2」を経て、今は「DELTA3」となりました。
このEFデルタはいちばん初期タイプ。このタイプも進化を遂げ、2を経て「Pro 3」。ひとつ前の2バージョンもまだまだ人気です。
これもさらに後発のニューモデル、「DELTA Max 1600」。
この容量なのに急速充電で1.7時間というのは驚異的でしょう。できるだけ急いで使いたい時でも助かりますね。
ちょうどアマゾンでタイムセール中でした。楽天でも5と0のつく日を狙うとポイントアップ。
さらに大きくなった「DELTA Max 2000」。後にわかりやすくW数がついているのが追加されたニューモデルですね。
同じくタイムセール中です。
こちらの「DELTA Pro 」は災害用ポータブル電源の頂点に立つ最終兵器かもしれません。
大容量なので、据え置きで使うのに適しています。
それでも容量の割には比較的コンパクトな作りのようです。
メーカー5年保証も嬉しいですね!
まとめ
いまや、いつ起こるかもしれないと言われている地震や噴火、または有事...。
そのため今回想定している防災対策は、数日や一週間というよりも、数ヶ月以上という長丁場向けで考えてみました。
はっきり言ってしまえばそれは未知数ともいえます。
とはいえ、貴重な体験談やプロはだしの方々の情報も山ほどあるという、その点ではすばらしい時代!
そして意外と、自分に必要な備えは、自分が何をどう使いたいかまで、ある程度は掘り下げて考えないとわからないものです。
ただ、急ぐ場合でも、ここにご紹介したポータブル電源を選べばとりあえず最高レベルの安心感と条件が揃っていると感じました。
防災には、大きなものからまず揃えてしまうのがおすすめと言っている人もいます。
ちょっとだけ時間を作れるあなたも、今からポータブル電源の選び方を身につけて少しでも早く安心しましょう♪
公式サイトからもお得に買えます。